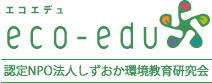かっぱ先生の川遊び教室、滝沢川でやってきました!!
今年はなんと!かっぱ2人?が9組29人の親子に
「かっぱ7ヶ条」を伝授してくれました。

そしてお昼にはスイカ割り。
おしい!おしい!の連続で、なかなか当たらないスイカを
割ろうと、みんなで声を出しあっていました。

川ではいろいろな種類の生き物を捕まえて、みんなで
観察もできました。もちろんかっぱ先生の教え通り
捕まえた生き物たちは、最後には、川へ帰ってもらいました。


今年も天候に恵まれ、みんなで楽しい川遊びができました。

「かっぱ7ヶ条」ちゃんと覚えました!!
「かっぱ7ヶ条」
第1条 履き物はかかとのあるものをはくべし!
第2条 流れたものは追いかけない!
第3条 水分と休憩をとるべし!
第4条 大人と一緒に遊ぶべし!
第5条 天気は山(上流)のほうを見るべし!
第6条 捕まえた生き物は返して帰るべし!
第7条 元の姿に戻して帰るべし!
年別アーカイブ: 2013年
【活動報告】夏の三日目!(7/29)
『雨を楽しむ!』
カッパがあれば、雨だってへっちゃら!

雨の日しか出会えない生き物がいるし、

雨を集めるだけでも楽しいね!

今日の一日〔ダイジェスト〕








里山やっほ7/3霧雨の中での生きもの探し
この日はザーッと降るような雨ではなく、シトシト降ってくる霧雨でした。
子ども達も大して気にせず、多少服が湿っても生きもの探しに集中していました。
軍田ヶ谷ダム近くでの小川で、ジッと何かを見つめる子ども達。
「見つけた!」
誰かが声を上げて動き出した。
近くにいた子ども達も顔を向けて近づいていく。
見ると、手のなかには小さなアカガエルが一匹、ひょっこり隙間から顔を出していました。

川の中には他にもいろんな生きものがいます。
小さな小魚が群れをなし、オタマジャクシが黒い点々となって佇んでいます。
石の裏や比較的水流の弱い川端を探すと、綺麗な川にしか住まないサワガニが現れます。
年長組の子ども達がそんな生きもの探しに熱中し、しゃがんで目を凝らして捕まえるチャンスを作ります。

年少、年中の子どもたちは竹での遊びに夢中です。
さとちゃんが伐った親指大程の太さがある竹を、水を入れてブクブクブク~。
別の子は縦に切れ目を入れた竹を吹いて、苦労の末ようやく音がなった驚きと嬉しさで、終わりの時間までピーピーピー。
竹一つでも遊びがこんなにも展開できました。
時期的に七夕が近かったので、子ども達一人一人笹を渡し、「笹の葉さーらさらー」と歌いながら今日の活動を終えました。
【活動報告】夏の二日目!(7/25)
【活動報告】夏の一日目!(7/24)
森での“出逢い”は、どれほど優秀なスタッフにも準備できないもの。
この夏、はじめての活動は小雨まじり。
山頂を目指して歩きはじめ、その出逢いは突然でした!

みんなが囲んだ、その視線の先には・・・

亡くなってしまった“モグラさん”がいたのです。
そんな時、子どもの集中力はすごいもので、押し合いもせず、静かに瞳を地面に向けます。
(みんな、なにを考えているのかな~)
森での出逢いは、子どもたちの心を揺すってくれたみたいです。
モグラさん、ありがとう。
今日の一日〔ダイジェスト〕






【拡大募集中!】夏休み小学生プログラム♪ 1dayだよ!
あっつい夏こそ、そとアソビ!
みなさんの声にお応えして、小学生向けやっちゃいます!
●第一弾 キャンプ満員御礼!*
「里山そとアソビ塾」夏キャンプ
★とき 2013年8月10日(土)~11日(日)*荒天中止
★場所 大久保キャンプ場(藤枝市の山奥)*テント泊
*集合解散は「藤の瀬会館」(藤枝市の瀬戸谷)
★対象 小学1~6年生(16名)
★参加費 一人14,000円
★申込み 締切ました!
★たとえばこんなことやる予定です
火お越しやバーベキュー、昆虫探し、望遠鏡で星空観察、源流で川遊びや魚を捕まえてみよう!
●さらに第二弾だよ! 8/9(金)まで延長 1年生のみんな集まれ~♪
『どっぷり里山アソビ!』
☆とき 2013年8月18日(日)・23日(金) 一日ごとの募集です♪
9:30~14:00
☆場所 エコエデュ事務所周辺の里山
☆対象 小学1年生 15名
☆参加費 一日ひとり2,000円
☆申込み 8/9(金)18:00まで
☆例えばこんなことやります!
川探険、生き物さがし、野菜の収穫、子どもから生まれたアソビ、などなど…
里山の山・川・畑をふんだんに使って、たっぷり遊びます!
里山いっぽ7/22泥だらけ大好き
今日の参加者は9名。
さとちゃんとぶんぶん、大人スタッフ含めると合計11人での活動です。
少し歩きたいということもあって、この日はまず畑に向かいました。
水をバケツに汲むため、途中事務所に寄って水を入れます。
初めは一人一個ずつバケツを持って水を入れていたのですが、
ひょんなことから一人の女の子がビニール袋に水を入れました。
透明なビニールですので、下からのぞくとお日様の光でキラキラしています。
それを見ていた子ども達が次々にバケツからビニール派へ移り変わります。
ビニール派とバケツ派に分かれ、水を入れた容器を持って一同畑へ。
向かっている最中、ピンクのバケツに水を沢山入れた女の子が、
えっちらおっちら運ぶのに苦戦しながらも、一生懸命に持って行きました。

糀が谷駐車場近くでお弁当を食べ、早く済ませた子達から炭焼き小屋近くの水場に行こうと思いましたが、
途中、水が引いた泥場を発見。
すぐさま泥んこ大好きな男のたちが入って行き、泥遊びを始めました。
思い思いに泥をつかみ取って、手でこねはじめます。
これはアイスクリーム、これは柏餅、ハンバーグやバナナ、作り方は様々です。

あまり汚れたくない子達も、さとちゃんが泥場から離れた場所に泥の塊を持っていくと、
恐る恐る指で押したり突いたりして感触を確かめています。
しばらくすると自分で持てる分だけの量を手に取ってこねはじめました。
汚れが気になるようなことも、こういう手のみが汚れるぐらいだったら、
本人も納得して遊ぶことができます。
遅れて食べ終えた子達も続々と泥場に入って泥んこ遊びを始めました。
遊びに夢中になった分衣服は泥だらけになります。
先に入っていた男の子達の中には全身ずぶぬれの泥だらけになり、
顔も泥水で濡らし、乾燥した後の顔面が白粉を塗った麻呂のようになった子もいます。
その分だけ、その子が思いっきり遊びきれた証になったと思います。
暑い日が連日続き、8月に入ればさらに温度は高くなります。
暑くなりすぎると子ども達の遊びの集中も途切れがちになってしまいます。
木陰や河辺で遊びながら子ども達の身体に蓄積する熱を上手く逃がし、
遊びの世界をどんどん広げていきたいですね。
【里山いっぽ】なぜ自然の中で?(4)
~私たちは、どうして子どもたちを自然の中に連れ出しているのでしょう。
子どもたちの姿を通して、野外保育の考え方をお伝えしていきます~
自然の中で過ごすことは「心の柔軟さ」を育みます。
暑い日が続きました。野外保育では、季節季節でフィールドを変えます。
今は、川遊びに最適の季節。存分に川遊びを楽しみます。
はじめ、子どもたちは水がかかるのを嫌がります。
顔にお水がかかったり、服がぬれたりすることに慣れていないようです。
でも、こんなに暑いとお水の心地よさを否応なく感じます。
はじめは、とまどっている子どもたちも
「お着替えあるから ぬれてもいいんだよ~」という
お友達の言葉をきき、「Nも、おきがえあるもん」と
遊びが大胆になっていきます。

服がぬれたり、汚れたりすることが当たり前になってくると、
お着替えも日常。
自分に降りかかる様々な状況に柔軟に対応していけるようになります。
また、自分でお着替えも上手になってきます。
【里山いっぽ】なぜ自然の中で?(3)
~私たちは、どうして子どもたちを自然の中に連れ出しているのでしょう。
子どもたちの姿を通して、野外保育の考え方をお伝えしていきます~
「好きなことがみつかること」
自然の中はその子の好きなことが見つかる場です、と書かせてもらいました。
「自分の好きがみつかること」は自己肯定感を育みます。
自己肯定感とは「自分のあり方を積極的に評価できる感情」といわれます。
言い換えると、
「自分はかけがえのない大切な存在」だと思える心。
この気持ちは、幼児期につくられていきます。
そして、無意識の中でつくられていく感情です。
Tくんお水遊びが大好きです。
お水の中で、お水と向き合っています。
好きなように川で、お水と戯れています。
ものや素材としっかり向きあえることは
自分ともしっかり向き合える基礎をつくります。
自分と向き合えることは、自分はかけがえのない大切な存在だと
認識していきます。
例え将来、挫折することがあっても、きちんと自分と向き合い
自分を大切にしていけるでしょう。
本物を知り、自分で考え判断していける人になります。
与えられた課題をこなすことで自分を評価していくこととは、出発点が違ってきます。
自らが主体的にものや素材とかかわり、遊びを生み出していくことが
自己肯定感を育むことはいうまでもありません。
【里山いっぽ】なぜ自然の中?(2)
里山いっぽはを主催している「しずおか環境教育研究会」は
「森のようちえん全国ネットワーク」に登録しています。
全国各地で、森や里山など自然の中で教育を行う団体が増えています。
なぜ、今、自然なのでしょう。
幼児が置かれている社会状況があると思います。
現代は大人にとって都合のよい、便利で快適な生活環境が整っています。
大人にとって、都合がよくても、
子どもにとっては、健全な心と身体の成長が妨げられてしまうのでは
ないでしょうか。
幼児期の子どもたちは、内なる自然に正直な
感性、感覚であらゆるものをとらえる存在です。
里山いっぽは自然の中で過ごすことを日常にすることを通して
自然の持つ教育力を享受し、その子がその子らしく豊かに育つ
過程を支援していきます。